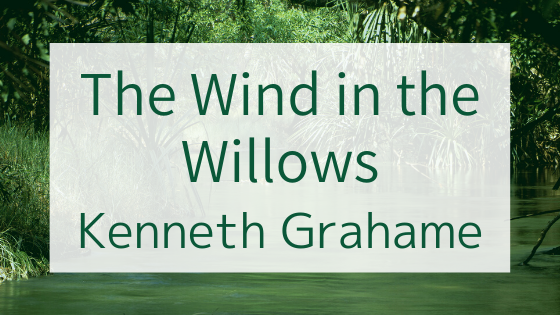1908年に発表された、かなり昔の作品です。
馴染みのない英単語に戸惑いつつも、古き良き時代の風を感じました。
擬人化された動物たち
この小説は、モグラくん(Mole)、ネズミくん(Water Rat)、カエルくん(Toad)、アナグマくん(Badger)の4匹が主役。
動物たちが川辺の自然の中で繰り広げる出来事が生き生きと描かれています。
面白かったのが、登場する動物がみな人間っぽい生活を送っているところ。
きちんとドアのついた家に住んでいたり、ボートや車に乗ったり、テーブルについて食事をしたり。
それぞれの動物としての特性が、擬人化された描写の間にひょっこり顔を出すが愉快でした。
カエルくんが洗濯婦になりすまして刑務所から脱獄する場面では、変装が割とうまくいっているのに失笑。
人間と動物の境目が適度に曖昧になった世界観は、のどかでいいなと思います。
モグラくんの涙にやられた
胸がジーンとなったのが、モグラくんが動物の本能によって、かつての住んでいた家の気配を感じ取る場面。
どんどん先へ進んでしまうネズミくんに、強く「止まって」と言えないモグラくんの気持ちがよくわかり、もらい泣きしそうになりました。
変に気を遣って自己主張し損ねてしまい、後からどうしようもなくなる感覚、今まで何度経験したことか……。
事情を察した後のネズミくんの対応がまた優しくて、非常に「刺さる」シーンでした。
物語の中心の4匹の中でいうと、僕は完全にモグラくんタイプ。
世の中には、ネズミくんみたいに心が広く、かつ周りを引っ張ってくれるような人が意外と多くて助かっています。
古風なイギリス英語に苦戦
『The Wind in the Willows』は100年以上前に書かれた作品で、文章中には普段目にしない古い英語が多数登場していました。
しかも、舞台はイギリスで、使われているのは典型的なイギリス英語。
単語を辞書で調べると<古>や<文>、<英>といった記号にたびたび遭遇し、児童書にしては意味を理解するのになかなかの苦戦を強いられました。
ereとかhitherとかthenceとか、響きはかっこいいんだけどなあ……。
一口に「英語」といってもいろいろなバリエーションがあって、現代のアメリカ英語だけがすべてではないのだと痛感しました。
さいごに
『The Wind in the Willows』は『たのしい川べ』というタイトルで和訳版も出ているようですが、僕は全く知りませんでした。
日本語だとあえて手に取らない児童書でも抵抗なく楽しめるのは、洋書の魅力の一つですね。
僕の英語年齢はたぶんまだ小学生以下なので、面白ければどんなに子ども向けの本であっても大歓迎です。